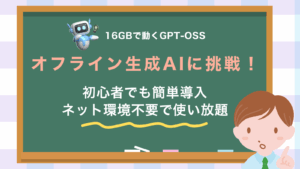AI時代のエンジニアとは?コードを書く力より大切な“問いの力”
コードは書ける。でもそれだけでいいの?
ChatGPTやGitHub Copilotなど、AIの進化は凄まじいスピードで進んでいます。
一昔前なら「このコードどう書けばいいんだ…」と悩んでいた場面も、今はAIに聞けば一瞬で答えてくれる時代になりました。
「じゃあ、もうエンジニアっていらなくなるの?」
そんな疑問を持ったことがある方もいるかもしれません。
でも、実は今こそ“人間エンジニアにしかできないこと”が、ますます重要になってきているんです。
それは「問いを立てる力」。
「何を作るべきか?」「どんな前提条件で考えるべきか?」そういった“考える力”こそ、AI時代の武器になるのです。
AIがコードを書いてくれる時代の到来
GitHub CopilotやChatGPTの登場
2021年に登場したGitHub Copilotは、エディタに書いたコメントやコードの流れから、次の行のコードを予測して書いてくれるツールです。
さらに、ChatGPTなどの対話型AIも、「〇〇をするPythonコードを書いて」と言えば、動くコードを即座に提示してくれます。
コーディング=スキル、という前提の崩壊
かつて「コードを書けること」がエンジニアの最大の価値でした。
しかし、AIがある程度のコードを書いてくれる今、その価値の比重は確実に変化しています。
「とりあえず書いて動かす」時代からの転換
大切なのは、「どう動かすか」ではなく「なぜそれを作るのか」。
つまり、課題をどう定義し、どんな解決策を設計するかが、エンジニアとしての価値を左右するようになってきています。
では、エンジニアに求められる役割は?
問題を定義する力
たとえば「予約機能をつけたい」という依頼が来たとき、それはカレンダー形式なのか?時間帯の制限はあるのか?
機能の背景や制約、目的を洗い出す力がなければ、AIに聞いても“的外れなコード”が返ってきます。
適切な質問をする力(プロンプト設計)
AIに「うまく」聞くには、質問の質が問われます。
「なんかバグが出る」ではなく、
「この関数の引数が undefined になる原因を教えてください」
といった具体的な聞き方が求められます。
ここで大事なのが、「バージョン情報を伝えること」。
AIは、古いバージョンの情報をベースに回答してくることがあり、
自分の使っている言語やライブラリのバージョンをプロンプトに明記することで、より的確な回答を得やすくなります。
AIが出してくる答えは、常に正しいとは限らない
AIが返してきたコードが動かないことはよくあります。
特に、APIの仕様変更やライブラリのバージョンアップに伴い、古い記述をそのまま返してくるケースも多々あります。
そんなときに重要なのが、
- 「エラーの内容を自分で確認する力」
- 「本当にそのコードが現状の環境で使えるのか検証する力」
AIはヒントにはなるけれど、最終的な判断と修正はあなたの役割なんです。
“問いの力”を鍛える方法
Why/What/Howで考えるクセをつけよう
- Why(なぜ):なぜこの機能が必要?
- What(何を):何を実現すれば解決?
- How(どうやって):それをどう実装する?
この3段階で思考を整理することで、「問いの質」がぐっと上がります。
自分で仮説を持ってからAIに聞く
いきなり「答え」を聞く前に、自分なりの仮説を立ててみることが大切です。
「この変数が null になってるかも?」と考えてからAIに相談すると、理解が深まり、成長スピードも加速します。
実例:“問いの質”がAIの出力を左右する
「このUIをいい感じにしてください」とAIに指示すると、なんとなく装飾されたコードが出てきます。
でも、「ユーザーが片手で操作しやすいUIにしてください」と具体的に指示すれば、レイアウトやフォントサイズまで含めて考慮された提案が出てくることも。
この差が、“問いの力”の差なんです。
まとめ:AI時代のエンジニアに必要な3つの力
- 問題を発見する力
- AIに的確に聞く力(バージョン情報の提示含む)
- AIの答えを吟味し、活用する力
AIはとても便利なツールです。
でも、それを「道具」として使いこなすのは“あなたの問いの力”です。
これからのエンジニアは、コードを書く人ではなく、問いを立て、AIと共に創る人。
さあ、あなたは今日どんな“問い”を立てますか?